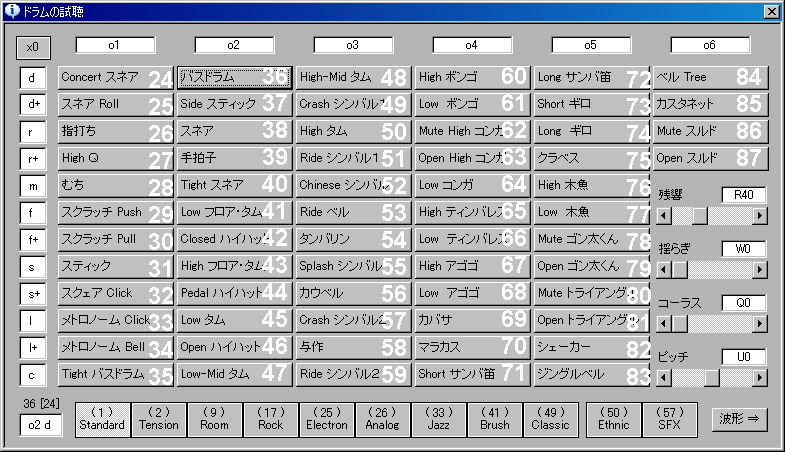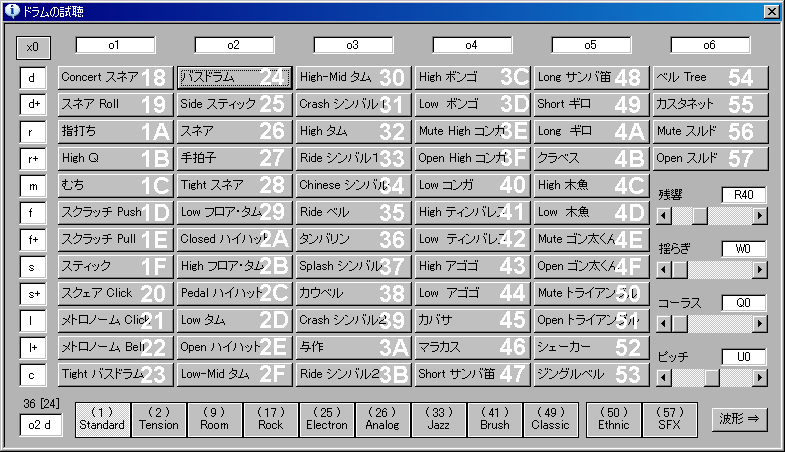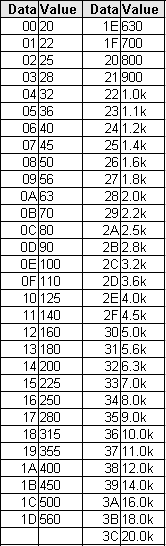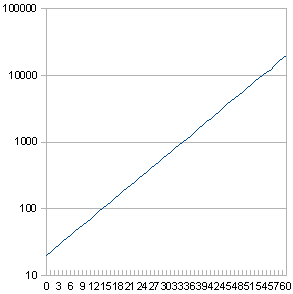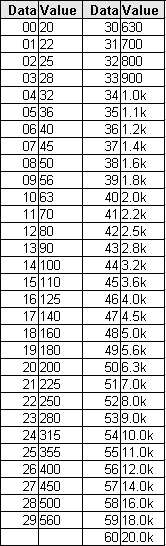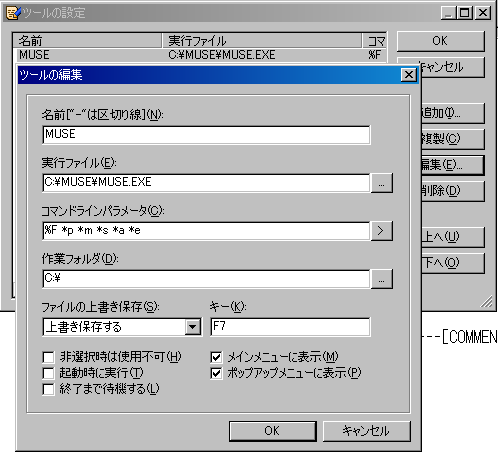|
*DATA "01, x"
*DATA "02, x"
*DATA "03, x"
*DATA "04,
x"
*DATA "05, x"
*DATA "06, x"
*DATA "07,
x"
*DATA "08, x"
*DATA "09, xh4,xl4"
*DATA "0B,
x"
*DATA "0C, x"
*DATA "0D, x"
*DATA "0E, x"
*DATA "0F,
x"
*DATA "10, x"
*DATA "11, x"
*DATA "12, x"
*DATA "13,
x"
*DATA "14, x"
*DATA "15, x"
*DATA "16, x"
*DATA
"17, x"
*DATA "18, x"
*DATA "19, x"
*DATA "1A,
x"
*DATA "1B, x"
*DATA "1C, x"
*DATA "1D, x"
*DATA
"1E, x"
*DATA "1F, x"
*DATA "20, x"
*DATA "21, x"
*DATA
"22, x"
*DATA "23, x"
*DATA "24, x"
*DATA "25,
x"
*DATA "26, x"
*DATA "27, x"
*DATA "28, x"
*DATA
"30, x"
*DATA "31, x"
*DATA "32, x"
*DATA "33, x"
*DATA
"34, x"
*DATA "35, x"
*DATA "36, x"
*DATA "37, x"
*DATA
"38, x"
*DATA "39, x"
*DATA "3A, x"
*DATA "3B, x"
*DATA
"3C, x"
*DATA "3D, x"
*DATA "3E, x"
*DATA "3F, x"
*DATA
"40, x"
*DATA "41, x"
...
*DATA "4C, x"
*DATA
"4D, x"
*DATA "4E, x"
*DATA "4F, x"
*DATA "50, x"
*DATA
"51, x"
*DATA "52, x"
*DATA "53, x"
*DATA "54,
x"
*DATA "55, x"
*DATA "56, x"
*DATA "57, x"
*DATA "58,
x"
*DATA "59, x"
*DATA "5A, x"
*DATA "5B, x"
*DATA
"5C, x"
*DATA "5D, x"
*DATA "5E, x"
*DATA "5F,
x"
*DATA "60, x"
*DATA "61, x"
*DATA "62, x"
*DATA
"63, x"
*DATA "64, x"
*DATA "65, x"
*DATA "66,
x"
*DATA "67, x"
*DATA "68, x"
*DATA "69,
x"
*DATA "6A, x"
*DATA "6B, x"
*DATA "6C, x"
*DATA
"6D, x"
*DATA "6E, x"
(備考)
x : パラメータ
(0-127)
xh4
: 上位4bit
xl4 : 下位4bit |
BANK SELECT MSB
BANK
SELECT LSB
PROGRAM NUMBER
Rcv CHANNEL
MONO/POLY
MODE
SAME NOTE NUMBER
KEY ON ASSIGN
PART
MODE
NOTE SHIFT
DETUNE
VOLUME
VELOCITY SENSE
DEPTH
VELOCITY SENSE OFFSET
PAN
NOTE LIMIT LOW
NOTE
LIMIT HIGH
DRY LEVEL
CHORUS SEND
REVERB SEND
VARIATION
SEND
VIBRATO RATE
VIBRATO DEPTH
VIBRATO
DELAY
LPF CUTOFF FREQUENCY
LPF RESONANCE
EG ATTACK
TIME
EG DECAY TIME
EG RELEASE TIME
MW PITCH
CONTROL
MW LPF CONTROL
MW AMPLITUDE CONTROL
MW LFO PMOD
DEPTH
MW LFO FMOD DEPTH
MW LFO AMOD DEPTH
BEND PITCH
CONTROL
BEND LPF CONTROL
BEND AMPLITUDE
CONTROL
BEND LFO PMOD DEPTH
BEND LFO FMOD
DEPTH
BEND LFO AMOD DEPTH
Rcv PITCH BEND
Rcv
CAT
Rcv PROGRAM CHANGE
Rcv CONTROL CHANGE
Rcv PAT
Rcv
NOTE MESSAGE
Rcv RPN
Rcv NRPN
Rcv MODURATION
Rcv
VOLUME
Rcv PAN
Rcv EXPRESSION
Rcv HOLD1
Rcv
PORTAMENTO
Rcv SOSTENUTO
Rcv SOFT PEDAL
Rcv BANK
SELECT
SCALE TUNING C
...
SCALE TUNING B
CAT
PITCH CONTROL
CAT LPF CONTROL
CAT AMPLITUDE
CONTROL
CAT LFO PMOD DEPTH
CAT LFO FMOD
DEPTH
CAT LFO AMOD DEPTH
PAT PITCH CONTROL
PAT LPF
CONTROL
PAT AMPLITUDE CONTROL
PAT LFO PMOD
DEPTH
PAT LFO FMOD DEPTH
PAT LFO AMOD
DEPTH
AC1 CONTROLLER NUMBER
AC1 PITCH
CONTROL
AC1 LPF CONTROL
AC1 AMPLITUDE
CONTROL
AC1 LFO PMOD DEPTH
AC1 LFO FMOD
DEPTH
AC1 LFO AMOD DEPTH
AC2 CONTROLLER
NUMBER
AC2 PITCH CONTROL
AC2 LPF
CONTROL
AC2 AMPLITUDE CONTROL
AC2 LFO PMOD
DEPTH
AC2 LFO FMOD DEPTH
AC2 LFO AMOD
DEPTH
PORTAMENTO SWITCH
PORTAMENT TIME
PITCH EG
INITIAL LEVEL
PITCH EG ATTACK LEVEL
PITCH EG RELEASE
LEVEL
PITCH EG RELEASE TIME
VELOCITY LIMIT LOW
VELOCITY
LIMIT HIGH |
[1]
[1]
1...128
(Channel)
MONO,POLY
SINGLE,MULTI,INST
NORM,
DRUM,
DRUMS1〜DRUMS4
[3] (半音単位)
-12.8 ...
+12.7[Hz]
[1]
[1]
[1]
RND,L63...R63
[5]
[5]
[1]
[1]
[1]
[1]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[3]
(半音単位)
-9600...+9450 (cent)
-100 ... +100
(%)
[1]
[1]
[1]
[3] (半音単位)
-9600...+9450
(cent)
-100 ... +100
(%)
[1]
[1]
[1]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[2]
(cent)
...
[2] (cent)
[3] (半音単位)
-9600...+9450
(cent)
-100 ... +100 (%)
[1]
[1]
[1]
[3]
(半音単位)
-9600...+9450 (cent)
-100 ... +100
(%)
[1]
[1]
[1]
0...95
[3]
(半音単位)
-9600...+9450 (cent)
-100 ... +100
(%)
[1]
[1]
[1]
0...95
[3]
(半音単位)
-9600...+9450 (cent)
-100 ... +100
(%)
[1]
[1]
[1]
[4]
[1]
[2]
[2]
[2]
[2]
1...127
1...127
(備考)
[1]
0...127
[2] -64...+63
[3] -24...+24
[4] OFF,ON
[5]
ノートナンバー |
0
0
0
ch
1
1
[1]
40h
64h
40h
40h
40h
00h
7Fh
7Fh
00h
28h
00h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
0Ah
00h
00h
42h
40h
40h
00h
00h
00h
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
40h
...
40h
40h
40h
40h
00h
00h
00h
40h
40h
40h
00h
00h
00h
10h
(X16)
40h
40h
40h
00h
00h
00h
11h
(X17)
40h
40h
40h
00h
00h
00h
OFF
00h
40h
40h
40h
40h
01h
7Fh
(備考)
[1]
Part10->2
others->0
|
X0=x
X32=x
Px
-
X126,X127
-
-
Tx
(RPN)
X7=x
-
-
Sx
-
-
-
Qx
Rx
X94=x
W=xx.
.
W= .xx.
W= . .xx
Q=xx.
Q= .xx
R=xx.
.
R= .xx.
R= .
.xx
X65=x
X5=x
|
受信するチャンネルを指定
単音モード/和音モード
ドラムパートを指定
(DRUM
SETUP や NRPN
を
受信できるようになる)
デチューン(0.1Hz単位)
ベロシティの感度指定
(cf.
Manual P83-P84)
発音域の指定
〃
(Var=SYS
のときのみ)
モジュレーション動作指定
〃
〃
〃
〃
〃
ピッチベンド動作指定
〃
〃
〃
〃
〃
チャンネルがメッセージを
受信するかどうか
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
スケールチューニング
CAT(Channel After
Touch)
動作指定
〃
〃
〃
〃
PAT(Polyphonic After
Touch)
動作指定
〃
〃
〃
〃
AC1(Assignable
Contoroller
1)として
指定するメッセージ番号
AC2
メッセージ番号
ピッチEG (cf. Manual
P80)
(立ち上がりからの
音程変化)を指定
発音するベロシティの
範囲を指定 |